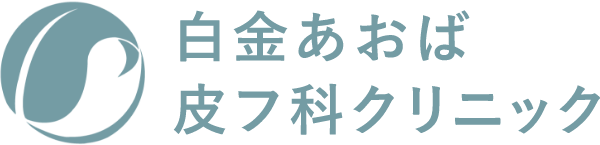イボ(疣贅/ゆうぜい)
- 1.イボ(疣贅/ゆうぜい)とは?
- 2.イボ(疣贅)ができる原因
- 3.イボ(疣贅)の診断方法
- 4.当院におけるイボ(疣贅)の治療法
- 5.生活の中で気を付けることは?
- 6.イボ(疣贅)のよくある質問 Q&A
1.イボ(疣贅/ゆうぜい)とは?
イボ(疣贅)は、主に皮膚や粘膜にできる、小さくて硬い隆起物です。一般的には、色は白や肌色、もしくは黒みを帯びていることもあります。この隆起物は、ウイルス感染によって生じるもので、特にヒトパピローマウイルス(HPV)が原因とされています。このウイルスは、皮膚や粘膜の細胞に感染し、異常な角質の増殖を促すことでイボを形成します。イボは放置しても自然に治癒することもありますが、多くの場合、見た目の不快感やかゆみを伴ったり、周囲の皮膚に広がったりすることもあります。
イボは性別や年齢に関わらず発生しますが、特に子供や若い成人に多く見られることがあります。外見や大きさはさまざまで、平らで滑らかなタイプや、突起が盛り上がったタイプなど多種多様です。また、感染する範囲も広く、接触や摩擦を通じてウイルスが他の場所や人へと広がる危険性があるため、注意が必要です。
この感染症は良性の腫瘍の一つですが、見た目の問題や不快感、長期間にわたる持続性などの点から、早めの適切な治療が望ましいです。イボは健康な皮膚の一部と見た目が似ているため、自分で判断せず、気になる場合は医療機関で正確な診断を受けることが重要です。
2.イボ(疣贅)ができる原因は?
イボ(疣贅)ができる主な原因は、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染によるものです。このウイルスは非常に多くの種類があり、皮膚や粘膜に接触することで感染します。感染した部分の皮膚や粘膜細胞にウイルスが侵入し、そこから増殖することで、イボが形成されます。
また、感染経路にはいくつかのパターンがあります。例えば、傷口やすり傷、擦り傷などの皮膚の小さな裂け目を通じてウイルスが侵入しやすくなります。特に、爪を噛む癖や皮膚を引っ張る行為、傷つきやすい場所に頻繁に摩擦がかかる場合には、感染リスクが高まります。公共の場所、たとえばプールやジムのシャワールーム、トイレの便座などは、ウイルスが付着していることもあるため注意が必要です。
免疫力の低下も感染のしやすさに深く関係しています。免疫機能が弱くなると、ウイルスに対する抵抗力が落ち、感染しやすくなるのです。例えば、ストレスや睡眠不足、栄養不足、また免疫抑制薬の使用などが免疫低下を引き起こすことがあります。
さらに、皮膚の乾燥や湿った環境も感染リスクを高める要因です。乾燥した皮膚はひび割れや裂傷の原因となり、そこからウイルスが侵入しやすくなります。一方、湿気の多い環境はウイルスが長時間生存しやすいため、感染の危険性が増します。
これらの要因が重なることで、ヒトパピローマウイルス(HPV)による感染が成立しやすくなり、イボ(疣贅)の発症や広がりにつながるのです。そのため、感染予防や免疫力を高めることが、イボの発症を防ぐ重要なポイントとなります。
3.イボ(疣贅)の診断方法
ウイルスによるイボ(疣贅)診断の多くの場合は、視診や触診で十分に判断可能ですが、より確実な診断を行うためには特殊な検査を実施します。その検査は「ダーモスコピー」と呼ばれる拡大レンズを用いたもので、ウイルスの影響によって毛細血管が拡張している様子や、表面の角質が厚くなっている状態を詳細に観察することが可能です。この方法は、ウイルス性イボの診断に非常に役立つだけでなく、治療の経過や効果判定にも用いられます。
また、患者様の職業や趣味、お子さんの習い事などについてなど、生活習慣をお伺いすることも診断の手助けとなる場合があります。
次の項目に当てはまる症状のある方は、ウイルス性のイボの可能性を考慮してください。イボは大きくなったり、数が増えたりすると、治療に時間がかかることもありますので、少しでも心配な場合は早めに受診されることをおすすめします。
・小さな隆起や突起
・表面がざらざらしている
・触ると硬い感触がある
・痛みやかゆみを伴うことがある
4.当院におけるイボ(疣贅)の治療法
- (1)冷凍凝固療法(液体窒素療法)
最も一般的な治療は液体窒素療法で、−196℃の液体窒素をイボに当てて組織を壊し、皮膚の再生を促します。数回の施術が必要で、痛みや副作用が出ることもあります。患者様の状態に応じて適切な方法を組み合わせて行うことも可能です。
- (2)内服薬(ヨクイニン)
ヨクイニンは、ハト麦の胚芽から抽出された漢方薬で、皮膚の新陳代謝を助け、イボや肌荒れの改善に効果が期待されます。長期間の服用でより効果が発揮されますが、副作用も少ない治療法です。ただし、妊娠中や授乳中の方は医師にご相談ください。
- (3) 外用薬(サリチル酸軟膏、スピール膏)
皮膚の表面にある角質をやわらかくして、イボの除去を促進します。特に、皮膚が硬くなった手足のイボに対して効果的であり、治療の一環として安全に使えます。これらの薬は保険適用での処方が可能です。
- (4)レーザー治療
局所麻酔下で炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)を使用し、イボを焼き切る治療法です。痛みや回復までの時間がかかることがありますが、冷凍凝固療法(液体窒素療法)の通院が困難な方にはレーザー治療をご提案する場合があります
- (5)トリクロル酢酸塗布
トリクロル酢酸は強酸性の薬剤で、イボの組織を壊す作用があります。痛みがほとんどなく、液体窒素療法が難しい子どもや痛みに敏感な方に適しています。治療は1〜2週間に1度通院いただき、患部に塗布し乾燥させた後、絆創膏で保護します。塗布当日の入浴時は、まず患部を洗ってから普段通り入浴可能です。ただし、粘膜部分や顔のイボには使用できません。
5.生活の中で気を付けることは?
清潔に保つ:患部を清潔にし、傷や湿った状態を避ける
触らない・潰さない:感染拡大や悪化の原因となるため避ける
靴や衣服の清潔:足の裏のイボには、通気性の良い靴や清潔な靴下を選ぶ
免疫力を高める:バランスの取れた食事や十分な睡眠を心掛ける
感染しやすい場所での注意:公共のシャワールームやプールでの感染予防
6.イボ(疣贅)のよくある質問 Q&A
Q1.イボは自然に治りますか?
多くの場合、免疫力が高まることで自然に小さくなったり、消失することもありますが、多くのケースでは長期間残ることが多く、また広がる恐れもあります。そのため、適切な治療を受けることをお勧めします。
Q2.イボは他人に感染しますか?
はい、イボは直接皮膚の接触や間接的な接触を通じて感染します。例えば、共有のタオルや靴、水泳や体育の授業での接触によって感染することがあります。感染予防のため、周囲に気を配ることが大切です。
Q3.イボはどんな場所にできやすいですか?
足の裏、指、手のひら、顔、首など、皮膚の摩擦や傷ができやすい箇所に多く見られます。特に足の裏のイボは痛みを伴うこともあり、注意が必要です。
Q4.イボの治療にはどんな方法がありますか?
代表的な治療法には、液体窒素を用いた凍結療法、薬剤を塗る方法、レーザーや電気焼灼などの外科的処置があります。症状や場所、状態に応じて最適な治療方法を選択します。
Q5.イボは再発しますか?
治療後に一時的に消失しても、完全にウイルスが排除されていない場合、再発することがあります。特に免疫力が低下している場合は、再発のリスクが高まるため、注意が必要です。
Q6.イボとほかの皮膚のイボの違いは何ですか?
イボは、ヒトパピローマウイルスが原因のウイルス性のイボですが、ほかにも脂肪腫や皮膚腫瘍などの良性や悪性の腫瘍と見た目が似ていることもあります。そのため、自己判断せずに医師の診断を受けることが重要です。
Q7.イボの予防策はありますか?
感染を防ぐためには、公共の場所での水分や湿気に注意し、個人のタオルや靴を共有しないこと、傷や裂傷を放置しないこと、免疫力を維持する食事や生活習慣を心掛けることが効果的です。早めに対処し、感染拡大を防ぐことも大切です。
東京都港区白金あおば皮フ科クリニックのご予約はこちらから
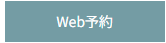

医療法人社団みなとあおば
理事長 菊地さやか
- 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
- 医学博士